チートデイ?リフィード?効率的に痩せる『代謝を戻す方法』の科学

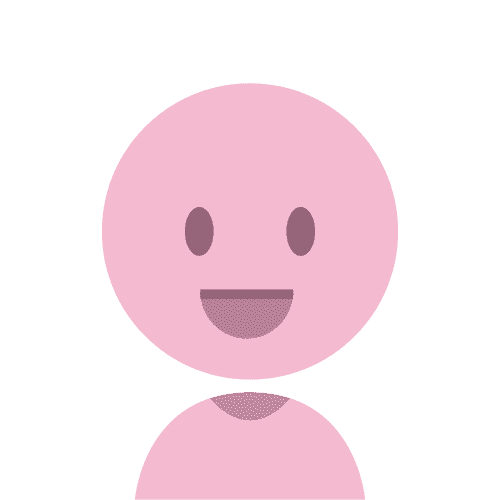
ダイエットで低下した代謝を戻して停滞期知らずになりたい!!!

ダイエットをしたことがあるヒトなら必ずぶち当たるこの悩み。
今回は代謝を戻す方法を徹底的に検証してみましょう
- チートデイが本当に効果があるのかがわからない
- リフィードという名前を聞いたことがあるけどイマイチ正しいやり方わからない
- 科学的に裏付けされた代謝を戻す方法を知りたい
今回は論文から「代謝を戻す方法」についてご紹介。
- 1日だけ爆食いするチートデイの効果
- 2-3日にわたってオーバーカロリーするリフィードは効果的
- 最近出てきた数週間維持カロリーに戻すダイエットブレイクの効果

代謝を回復させる方法を学んで停滞期知らずを目指しましょう
動画はこちら
ダイエットで代謝が低下するワケ
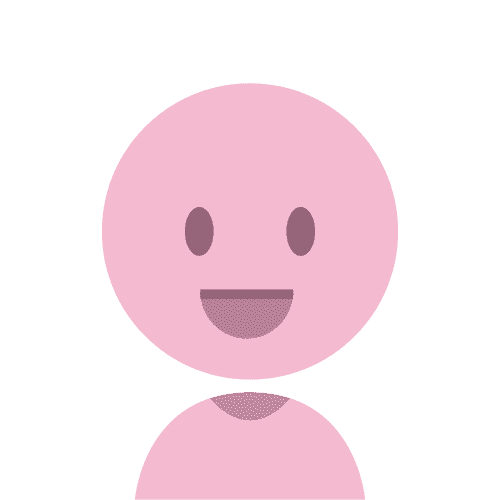
そもそも大前提としてダイエットで代謝が低下するというのは本当なの?

残念ながらこれまでの研究でダイエットで代謝が下がることはほぼ確実です
ダイエットによる代謝の低下を専門用語で「代謝適応(metabolic adaptation)」というが、この現象が起きることは多くの研究で確認されている。
代謝がどれだけ下がるのかについては議論の余地があるが、多かれ少なかれ代謝が下がるのは確実。

今までは運動習慣のない肥満の人を対象にした研究ばかりでしたが、最近になってトレーニーでも代謝の低下が確認されるようになりました
20人の若者トレーニー(男性5人&女性15人)を対象にした研究。
2週間にわたって-37.5%のカロリー制限をしてもらったところ、安静時代謝率が1602kcal→1508kcalまで下がった。

被験者は2.2g/体重のタンパク質を摂取しながら筋トレに励みましたが代謝の低下は止められませんでした
高タンパク質下で筋トレをしていようと被験者は5.9%の代謝低下を経験し、研究者は以下のように結論づけた。
トレーニーにおいて、2週間にわたる37.5%のカロリー制限は有意な代謝低下を引き起こした。高タンパク質と筋トレは、これらの代謝適応を和らげることはできなかった。
Madelin et al, 2020
およそ100kcalの代謝低下を問題とするかどうかは個人の主観による部分が大きい。
しかしダイエットをしている限りどうしても代謝低下そのものを避けることができないのだ。
代謝を回復させるには摂取カロリーを変化させることが大事

これらの代謝低下を防ぐためには、摂取カロリーを一定にしないことが大事です
ダイエットによる代謝の低下を防ぐには、摂取カロリーを一定にしないこと。
具体的にいうとダイエット中にずっとカロリー制限をするのではなく、一時的に摂取カロリーを増やすのだ。
専門用語で「間欠的エネルギー制限(Intermittent Energy Restriction)」と呼ばれるこの方法には、量と期間によって3つの方法が存在する。(R)
| 名前 | 量 | 期間 | 効果 |
|---|---|---|---|
| チートデイ(チートミール) | 爆食い | 1日(1食)だけ | △ |
| リフィード | 維持カロリー+40%ほど | 2-3日 | ⚪︎ |
| ダイエットブレイク | 維持カロリー | 数週間 | ◎ |

間欠的エネルギー制限は”量”と”期間”によって呼び名が変わりますが、どれもコンセプトは共通して「代謝の低下を防ぐ」です
そして大事なのは”期間”のほうで、一度に大量に食べるよりも長期間維持カロリーに戻したほうが代謝が回復することがわかっている。
ちなみにこれらの間欠的エネルギー制限は「ダイエット・ピリオダイゼーション」とも呼ばれる。(R)
ダイエット・ピリオダイゼーション:減量効果を最大化するために変数(摂取カロリー・栄養素)を操作すること
Brandon et al, 2020
日によって筋トレのボリュームや強度を変えるピリオダイゼーションのように、日によって摂取カロリーを変えるのでこの呼び名がついている。

何やら難しい言葉がついていますが、ようは「たまには摂取カロリーを上げる」というだけです
どちらの言葉も直観的に分かりづらいので、この記事ではまとめて「代謝回復戦略」と呼ぶことにする。
- 代謝を戻すには一時的に摂取カロリーを上げることが大事
- 代謝を戻す方法は間欠的エネルギー制限やダイエットピリオダイゼーションなどと呼ばれる
- 量と期間によって種類分けされ、代謝の回復に重要なのは量より期間
代謝回復戦略①チートデイ

まず最初に紹介するのはみんな大好きチートデイです
世間一般的にはよく行われるチートデイだが、実際に代謝適応を阻止できた直接的な証拠は(自分が知る限り)存在しない。
2010年の研究に行われた研究で「1日で8100kcal摂取したらホルモンであるレプチンのレベルが正常に戻った」という研究はあるが、代謝を直接計測した研究でチートデイの効果を証明した研究はない。

1990年代の時点で「たった1日のオーバーカロリーでは代謝が戻らないらしい」とわかっていたのでチートデイはあまり研究されていません
1998年に行われた研究ではチートデイではホルモンバランスが回復しなかった
実際に「1日のオーバーカロリーではホルモンバランスが戻らない」ことを示したのが、1998年の研究。(R)
普通体型の女性を対象にした研究。1000kcal/日という激しいカロリー制限をしてもらった後、オーバーカロリーを24時間続けてからホルモン値を測定した
ちなみにこの研究で測定されたのは「黄体ホルモンパルス(Luteinizing hormone pulsatility:LH脈動性)」と呼ばれるもの。
黄体ホルモンパルスは女性の月経不順や無月経を予測する。
黄体ホルモンパルスが乱れる=月経不順や無月経になる、を意味する。
この研究ではダイエットにより黄体ホルモンパルスが乱れたこと、そしてその後24時間にわたって4000kcalのオーバーカロリーにしても黄体ホルモンパルスの乱れは回復しなかったことが報告された。

簡単に言うと、ダイエットで乱れたホルモンバランスはチートデイでは回復しなかったことになります
1日で4000kcalという大量のカロリーを摂取したにも関わらず、ダイエットで乱れたホルモンバランスは回復しなかったのだ。
1995年に行われた研究ではリフィードによってホルモンバランスが回復した
同様の研究が1995年にも行われており、条件の違いは一つだけ。(R)
24時間のオーバーカロリーではなく48時間時間の維持カロリーにしたのだ。

この研究はチートデイではなくリフィードの実験になります
その結果として先ほどと同様にダイエットで黄体ホルモンパルスが乱されたが、48時間の維持カロリーでは黄体ホルモンパルスが回復したことが報告された。
- ダイエットでホルモンバランスが乱される
- 乱れたホルモンバランスはチートデイでは戻らない
- 乱れたホルモンバランスを回復させるには2日間の維持カロリーが効果的だった

30年近くも前から代謝を回復させるためには量だけでなく期間も重要だということがわかっていました
そしてこの「実施期間の長さが大切!」という概念は今でも全く色褪せておらず、比較的最近の2019年の論文でもはっきりと書かれている。(R)
カロリー制限による代謝適応を逆転させるという意味では、現在あるエビデンスはエネルギー摂取量だけでなく、オーバーカロリーにする実施期間も重要であることを示している。
Jackson et al, 2019

30年前から1日の爆食いでは代謝を戻すのが難しいと認識されていたので、今でもリフィードなどのほうがよく研究されています
チートデイの心理効果は大きい
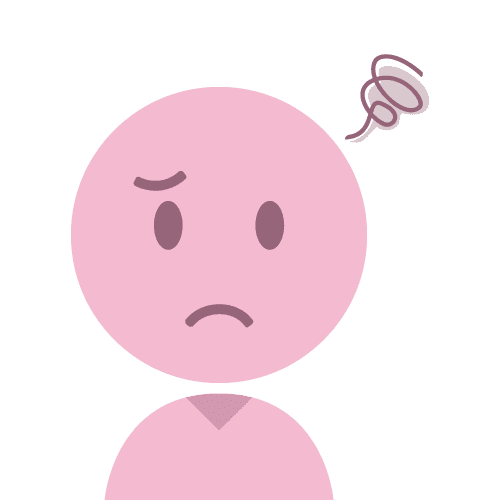
でも実際にダイエットで成功している人でチートデイを取り入れているヒトは多いのでは?

チートデイには心理的メリットがあるので、実際に代謝が上がらないにしろ取り入れているヒトは多いのでしょう
チートデイを実践したことがあるヒトならわかると思うが、チートデイのような”計画された失敗”はダイエットに絶大な効果を発揮する。
チートデイを設定しないと「どうしても食べたい!」という気持ちを自制するのが難しいからだ。
食欲が湧いてしまったときに『食べないようにしよう』と禁止するのは不可能に近い。
しかし『チートデイのときに食べよう!』と食欲を先延ばしにすることは簡単。

人間は”先延ばし”が得意なので、ダイエットでうまく使えば絶大な効果を発揮します
このことは実際の研究でも示されている。
週1回の計画された失敗日(=チートデイ)を作った人は、ぶっ続けでダイエットし続けた人よりダイエットのモチベーションが高かったことが判明している。

それじゃあやっぱりチートデイは入れるべき?

そういうわけでありません。
論文にも書かれていますが肝心なのは”定期的&計画的”な失敗日だからです
要するに欲求を先ばしにする期間があればいいので、チートデイではなくリフィードやダイエットブレイクでも問題ない。
むしろ代謝が戻る確証がないチートデイをするよりも、実際に代謝を測定した研究で効果が確かめられているリフィードやダイエットブレイクを取り入れるほうがいいだろう。
- チートデイは代謝を直接測定した研究が皆無
- チートデイではホルモンバランスが戻らない可能性が高い
- チートデイは心理的メリットもあるが、それはリフィードやダイエットブレイクも同じ
代謝回復戦略②リフィード
短期的な研究で糖質によるリフィードが効果的なことが判明した

1990年代の研究でホルモンバランスを回復できることが証明されたリフィードですが、実際に代謝を測定した研究でも効果があることが判明しています
リフィードの研究として有名なのが2000年のパドヴァ大学による研究。
健康な女性10人を対象にしたもの。3日間にわたる-50%という激しいダイエットをしてもらった後、3日間にわたる+40%のリフィードを実施した。
このとき、被験者には糖質過多と脂質過多の2パターンでリフィードをしてもらっている。
- 糖質メイン:糖質64%, 脂質25%, タンパク質11%
- 脂質メイン:糖質35%, 脂質55%, タンパク質11%

一方のグループは糖質をがっつり摂取し、もう一方のグループは資質をがっつり摂取しています
そして3日間にわたるリフィードの後、代謝に関係するホルモンであるレプチンと1日の消費カロリーを測定した。






