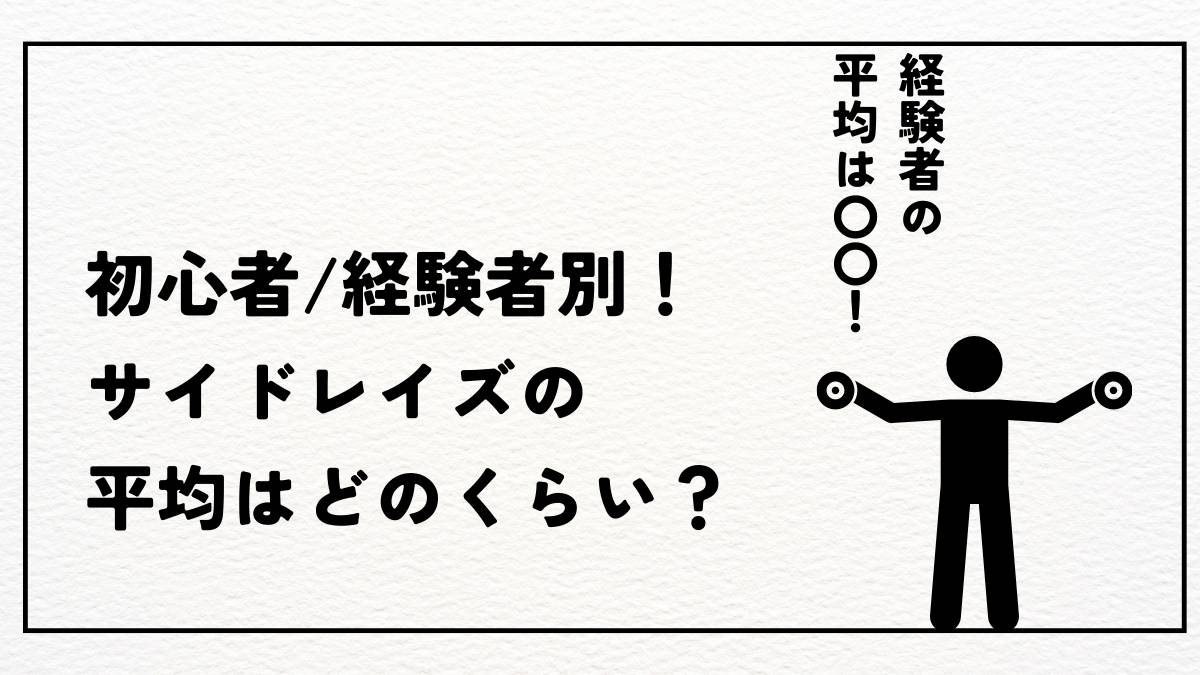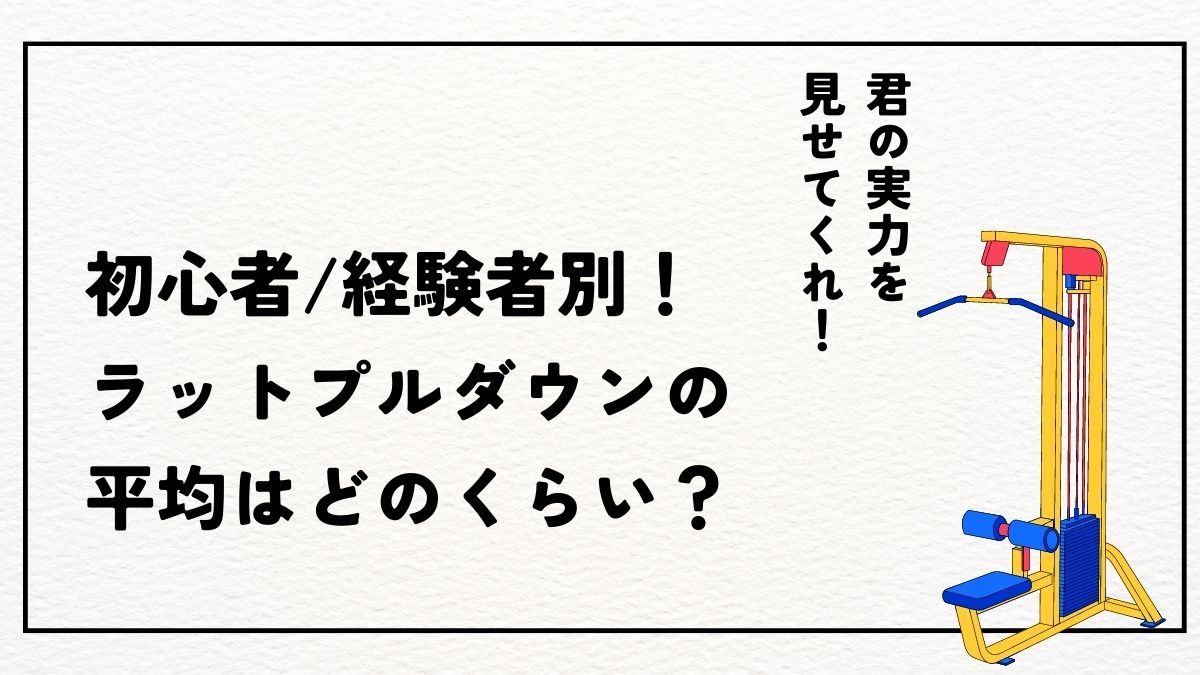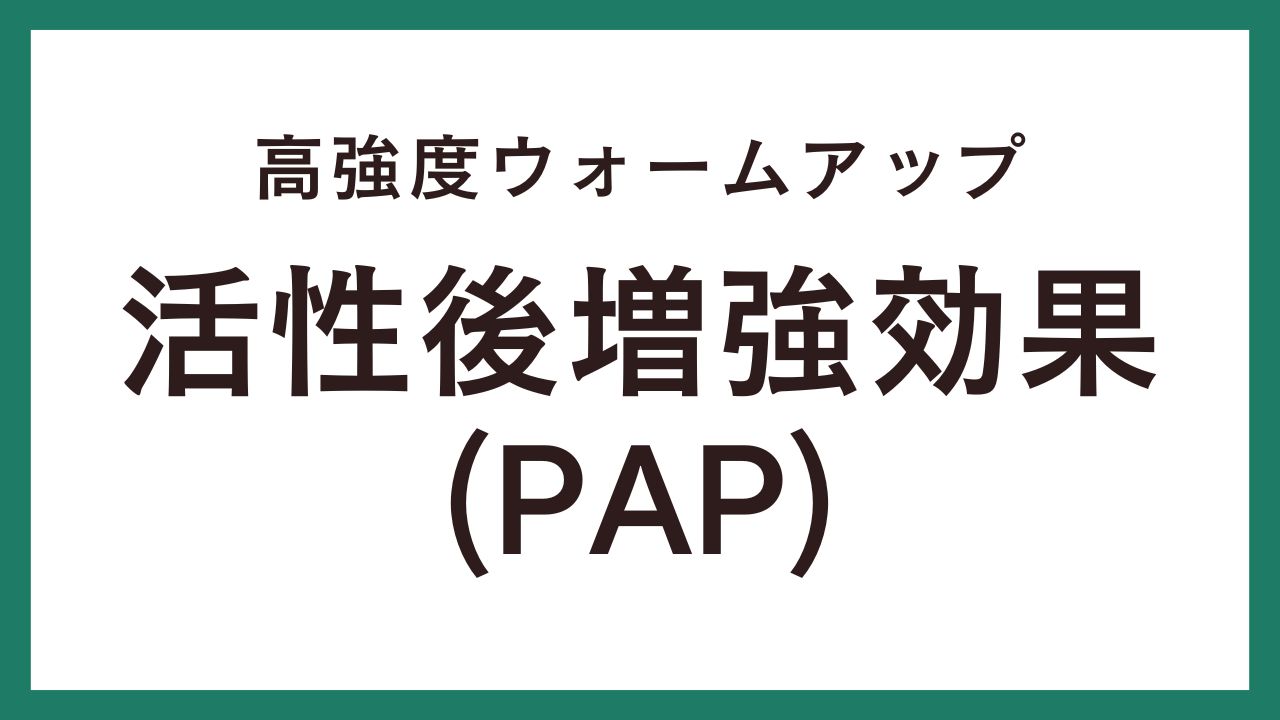筋トレのピリオダイゼーションとは?理論から実践まで論文で徹底解説

In research, when we're putting it into practice, we need to have two words in mind, "conceptualize" and "integrate".
Michael C. Zourdos
-筋トレ 研究を実践に取り入れるとき、2つの言葉を心に留めておかなければならない。それが”コンセプト”と”統合”である -
これは、筋トレ研究者マイケルによる言葉である。
研究結果を自分で利用するためには、そのコンセプトを理解せよ!とのこと。
さすがマイケル、いいこと言うぜ。
今回から始まるシリーズは”トレーニングメニューの作り方”である。
このシリーズの目標はただ一つ。
あなたが自分で一からトレーニングメニューを考えられるようにすることである。
ここで普通だったら「週に何セット腕トレをしよう!」…みたいなところから入るところをあえて”ピリオダイゼーション”から話を始める。
なぜなら、それがトレーニングメニュー作りのコンセプトを理解するのに一番近道だからである。
そして、この記事では『月曜日に60%1RMでスクワットをやって…』みたいな話も出てこない。
そんなことはコンセプトを理解すれば自分で決められる(とマイケルは言っている)。
というか、そういった指針はどうしても提示できないのである。それがなぜか?と言うのは、この記事を最後まで読めばわかる。
”筋適応”を最適化するのがピリオダイゼーション
そもそもトレーニングメニュー作りとは何?という話。
以前までの話のおさらいだが、筋トレだろうと有酸素だろうとトレーニングに対する筋適応は3つの変数で決まると言った。
- 強度:1RM, RPE
- 量 :ボリューム
- 頻度:週◯回
ということは、裏を返せば筋トレにおいて決めなければならないのも当然この3つの変数である。そして、この作業にはちゃんとした名前がついている。(R)
ピリオダイゼーション:筋適応を最大化するためにトレーニング変数(強度・ボリューム・頻度)をプランニングすること
Buford et al. 2007
これはまさにトレーニングメニュー作りそのもの。なので、ピリオダイゼーションから話を始めようと言ったのである。
「いやいや、待て。なんでそんな基礎的な概念ならピリオダイゼーションが世間一般…少なくともトレーニーの間で知名度が低いわけ?」と思うかもしれない。
これはもっともだが、これはなにも研究者がピリオダイゼーションを秘密の研究成果としてひた隠しにしていたからではない。
それは、単に世間は”筋適応を最大にすること”に対して興味がないからである。
これは別に「筋トレするやつなんて世間一般からしたら珍しい部類だから」みたいな話ではない。(まあ1%くらいはあるかもしれないが)
この話の根幹は「そもそも最大化したい筋適応とは何か?」ということにある。先ほどの3つのインプットのアウトプットとして出てくる筋適応は2つの要素からなる。(R,R)
筋適応 = 筋肥大(hypertrophy)× 神経適応(Neural Adaptation)
運動をすると、それに合わせて筋肉が大きくなる。
それに加え、神経系も要求された運動に最適化するように配線し直されるのである。
筋トレでは筋肥大ばかりに目がいくが、神経適応は特にスポーツで特に重要な概念。
野球少年がなぜ何回も素振りをするのか?
それは神経適応を進めてスイングを上達させたいからである。
決して筋肉を大きくしたいわけではない。
そして、そんな野球少年が大人になりプロ野球選手を目指すようになったとしよう。
そのとき野球青年が筋トレを始めるようになったとしても、それは急に思春期になりマッチョな体に目覚めたからではない。
それはパワーがあるほうが有利だから….すなわち”筋力”を高めたいからである。
そして、筋力とは”筋肥大”と”神経適応”の掛け合わせで決まる。
筋力 = 筋肥大(hypertrophy)× 神経適応(Neural Adaptation)
筋肉が大きくなっても筋力は上がるし、神経適応が進むことも筋力の向上に寄与している。
特に筋トレ初心者が筋肉がつくより先に重量がガンガン上がるのは神経適応の成せる技である。(R)
そして、ピリオダイゼーションで最大化したいのは筋適応、すなわち筋力のことである。
決して筋肥大だけではなく、神経適応も入ってくる。
ここが世間と研究界で需要のギャップが生まれている理由である。
世の中には2種類のトレーニーがいる
筋トレしている理由は人によって様々…とはいえ、この世には2種類のトレーニーしかいない。
- アスリート型 :スポーツのパフォーマンスを上げるため、筋力を高めたい。その手段として筋肥大と神経適応の2つがある。
- ボディビルダー型:筋肉のある見た目を作るため、とにかく筋肥大したい。筋肥大は手段の一つなんかではなく、目的そのもの。神経適応とかどうでもいい、見た目に関係ないし。
まず、アスリート型のほうがトレーニングが複雑になりがち。
なぜなら、筋肉を大きくすることに加え、神経適応も考えなければいけないからである。
これがアメリカで「(極端なアスリート型である)パワーリフターはボディビルダーのようにも鍛えよ」と言われる所以である。
筋肥大も筋力向上の大事な一要素、決して無視することはできない。
一方で、ボディビルダー型のほうはめっちゃ単純である。
神経適応なんかガン無視で、筋肥大だけをひたすら考えればいいからである。
神経適応が起こっても、見た目なんかクソほども変わらないからである。
そして、研究が進んでいるのは当然”アスリート型”のほうである。
なぜなら、研究では”社会的な意義”も大事な要素だからである。
筋トレ研究は往々にして『アスリートが勝つためには…』みたいな書き出しで始まるもの。
決して『最近はモテボディに関心のある人が多く…』なんていうふざけた書き出しではない。
これはダイエット研究の被験者の多くが”肥満”なのと同じである。
肥満という社会問題を解決することに意義はあるが、健常者を痩せさせてモテボディにしても仕方ないのである。
何はともあれ、アスリート型の方法論はよく研究されており、その結果”ピリオダイゼーション”なんていうかっこいい名前まで付けられているのである。
じゃあ私たちのようなボディビルダー型はどうなのか?もちろん筋肥大だけを高めることに研究界では需要がないのでほとんど研究されていない。
一方で、世間一般ではボディビルダー型はもちろんたくさんいる。
そして、往々にして筋力には対して興味がない。なのでボディメイク界隈ではピリオダイゼーションはほとんど知られていないのである。
このマガジンのコンセプトは見た目づくり。
よって、例のごとく筋力を最大化するピリオダイゼーションも飛ばす…かと思いきや、今回はしない。
ピリオダイゼーションは”筋肥大”と”神経適応”の両方を同時に高め、筋力を最大にする方法論である。
細かい話は抜きにしても、基本的な理論は理解しておいて損はない。
そして、ピリオダイゼーションはぶっちゃけ使わなくても全然構わないが、この概念にはボディビルダー型も得るものがある。
ということで、前置きが長くなったが「ピリオダイゼーション」の話を始めよう。