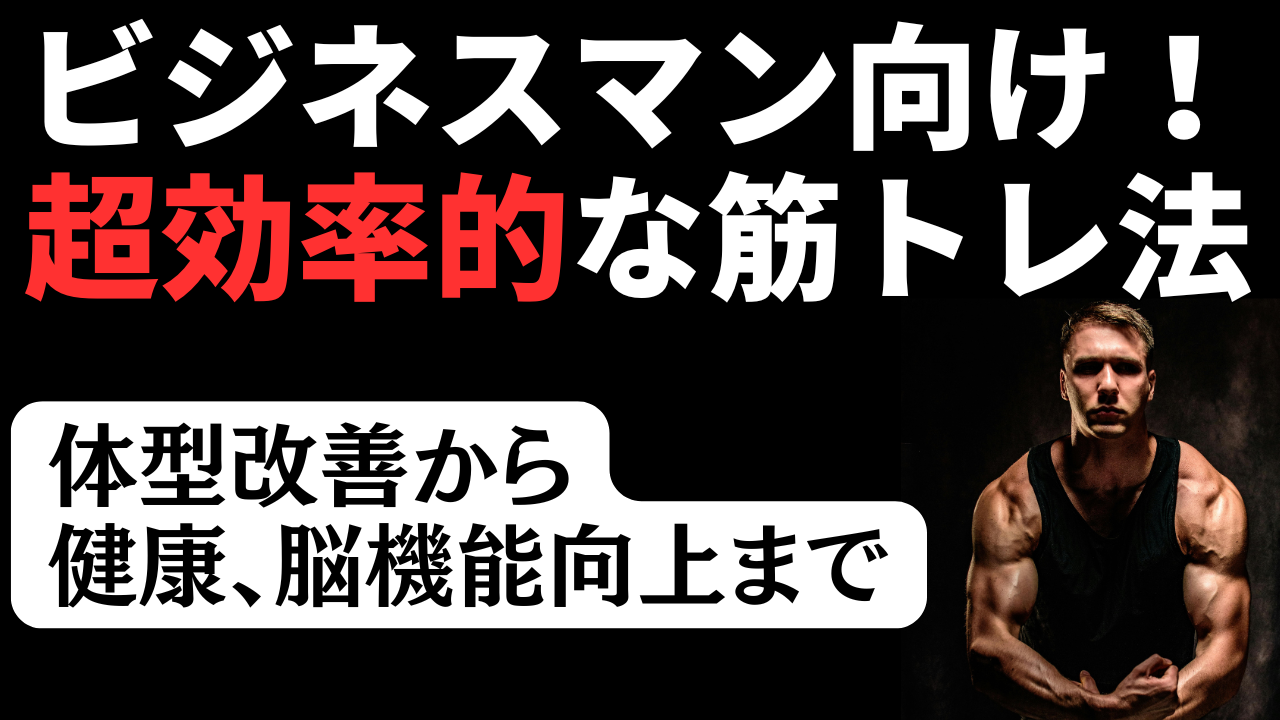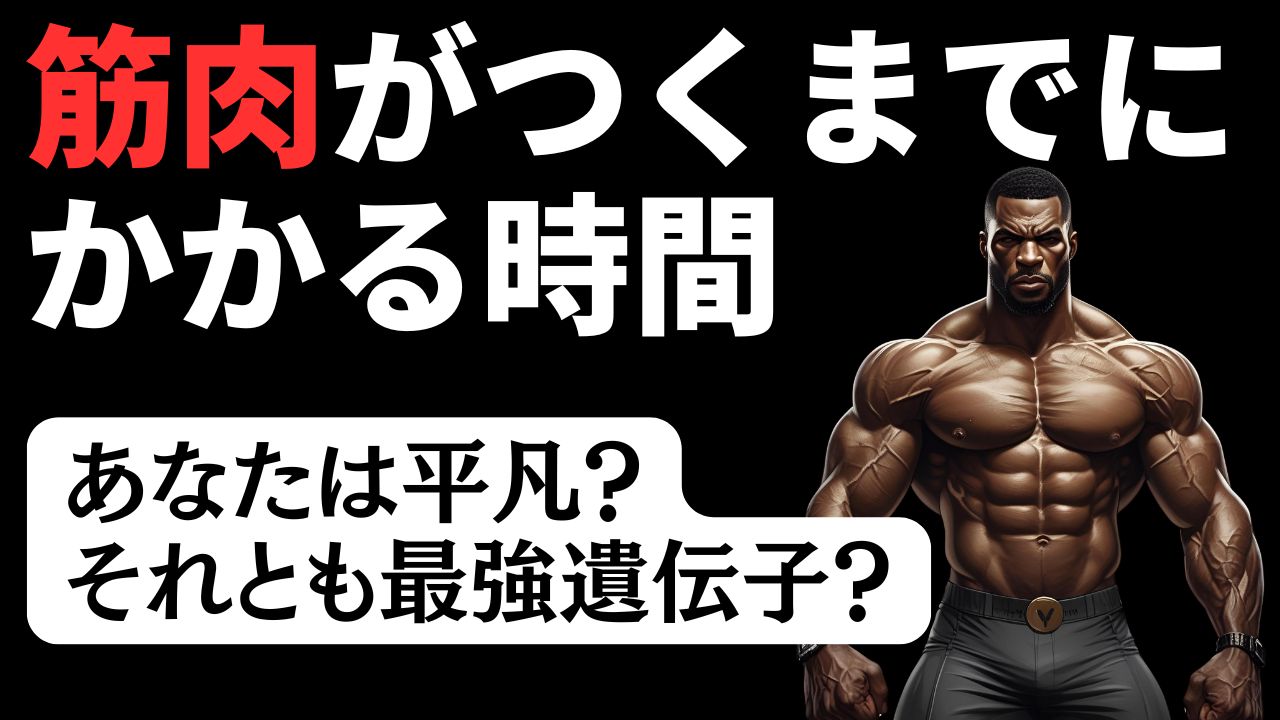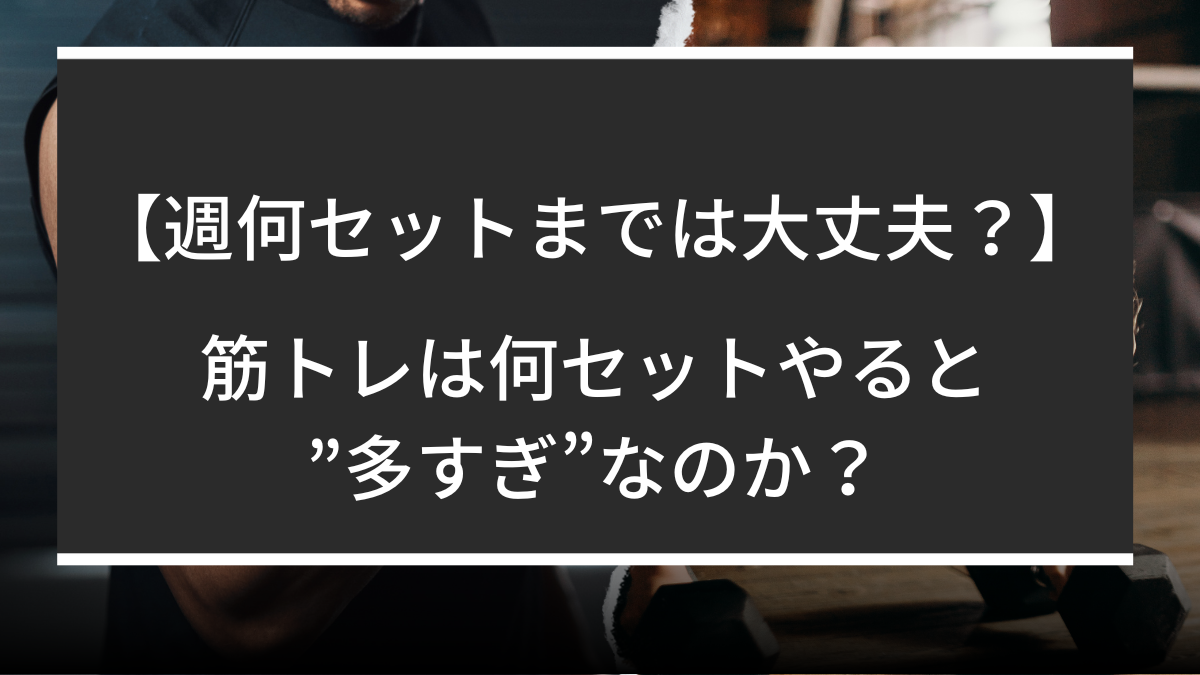筋トレを始めたい人向け「強度・頻度・ボリューム」まとめ
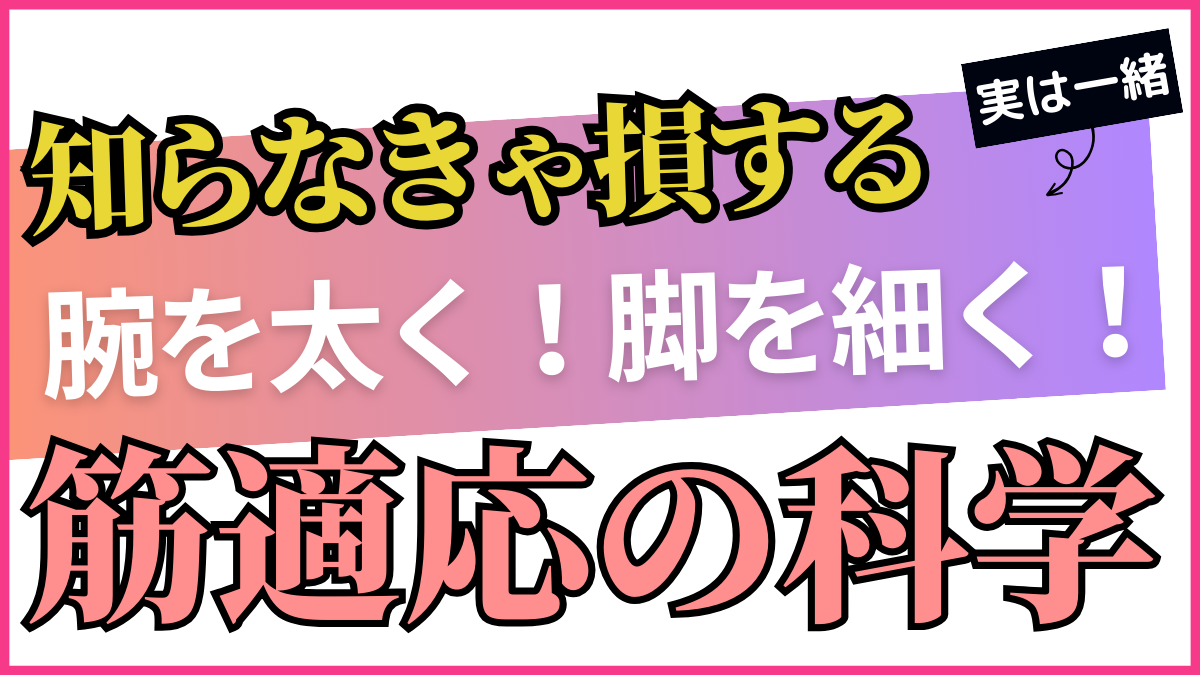
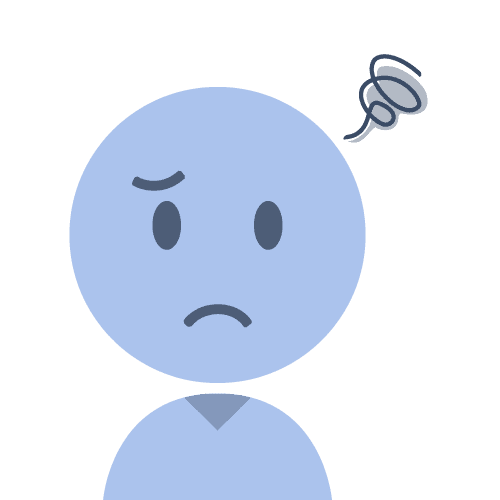
筋トレをこれから始めたいけど、何から考えたら良いかわからない!

筋トレを始めるとき、「強度・ボリューム・頻度」の3つを知っていればなんとかなります
見た目を変えたくて筋トレを始める人にとって、自分で決めなければいけない要素は実は3つだけ。
- 強度:どれくらいの”重さ”でやるのか
- ボリューム:どれくらいの”量”をやるか
- 頻度:週何回やるのか

スクワットだろうと足パカだろうと、筋トレで考えるべきはこの3つだけです
この3要素に加えて、無酸素運動と有酸素運動がどのように筋肉に影響を与えるかを知ることがトレーニングでは大事。
- 有酸素運動は筋肉が細く、無酸素運動は筋肉が太くなる
- 筋トレの”強度”は筋力に影響する
- 筋トレの”ボリューム”は筋肥大に影響する
- 筋トレの”頻度”は脇役的な立場

ヒトの見た目は「筋肉の太さ×脂肪量」で決まります。
今回はその中でも”筋肉の太さ”に関する話です。
動画はこちら
筋トレは筋肉を太くし、ランニングは筋肉を細くする
タンパク質の束である筋肉だが、見た目作りに重要なある性質がある。
それが”筋適応”という概念。
筋肉はインプットされた運動に対して”性質的にも形態学的にも”適応する(R)

筋肉は日々の生活で要求される運動がラクにできるように適応する性質があります
日々の運動に適応する筋肉だが、適応の種類はざっくりと「無酸素適応」と「有酸素適応」の2つがある。
| 運動 | 組織 | 筋肉の見た目 | |
|---|---|---|---|
| 無酸素適応 | 高出力/短時間 | 筋肉のサイズUP 神経適応UP | 太くなる |
| 有酸素適応 | 低出力/長時間 | 毛細血管量UP ミトコンドリア量UP | 細くなる |
有酸素運動を続けると、酸素の運用能力が上がって長時間の運動に耐えられるようになる。
一方で無酸素運動は筋肉のサイズが大きくなり、一度に多くの筋肉を動員できるように神経適応が進むことで瞬間的に大きな力が発揮できるようになるのだ。

見た目の変化だけでいうと、無酸素運動は筋肉が太くなるのに対して有酸素運動では筋肉が細くなります
無酸素運動に特化しているボディビルダーが太い筋肉を持っているイメージがあると思うが、実は有酸素運動に特化しているマラソンランナーというのは筋肉が細い。


嘘だと思う人は”駅伝”などとGoogleで検索してみてください。細身の人が多いことに気づくはずです
有酸素運動に適応すれば筋肉は細く、無酸素運動に適応すれば筋肉は太くなるのだ。
筋肉の適応には”特異性”がある

もし足を細くしたければ有酸素運動をすればいいってこと?

その通りです。逆にゴツい足を手に入れたければ筋トレをすればOKです
筋適応を実際の見た目作りに応用しようとするとき、一つ知っておかなければならない概念がある。
それが”特異性”である。スポーツ科学の専門用語でいうところの"SAID principle”だ。
”Specific Adaptation to Imposed Demand"の略でSAID。日本語で言うと「要求に対する特異的な適応」となる
特異性などと言ってるが、簡単に言ってしまえば「筋肉は要求された運動だけに特化した適応をする」ということだ。(R)
筋適応は、運動で使った部位のみに起こる。
例えばスクワットでどれだけ脚をいじめ抜こうとも、腕に無酸素適応が起こり「いつの間にか太くなっていた!」という事態にはならない。

筋トレであれば鍛えた部位以外の場所が太くならない、というごく当たり前のことです
そしてもう一つ、無酸素運動と有酸素運動にも”特異性”があるのだ。
ボディビルダーが有酸素運動をしない理由
筋適応は、要求された”運動”にのみ特化する。
例えばランニングをしていたのに、脚に無酸素適応が起きていてボディビルダー並みに太くなっていたということはない

そして有酸素運動と無酸素運動は互いに相反する適応なので、どちらかの適応が進めばどちらかの適応が犠牲になりがちです
実際に筋トレの世界には「同時トレーニング」と言う概念がある。
有酸素運動をすると筋肥大が阻害されるという考え。
一般人にとっては有酸素運動と筋トレを同時に行っても問題ないが、どちらかの適応を極める必要があるマラソンランナーやボディビルダーにとっては死活問題。
有酸素運動をすると多少なりとも筋肉の適応は”筋肉が細くなる”ほうに引っ張られるので、彼らは有酸素運動をほとんどしないのだ。

ちなみにこれらの特異性は厳密にいうと間違っています
例えば、片脚をトレーニングしたらもう一方のトレーニングしていない脚の筋力が上がったり、全く運動をしてこなかった人が高強度のサイクリングをすると筋肥大するという話もある。(R,R)
実際のトレーニングは多かれ少なかれ持久的運動でもあり筋力的運動でもある。純粋な筋力運動や持久系運動というものは存在しない。(R)
どんな運動も”筋力-持久力連続体(strength-endurance continuum)” のどこかに位置しており、完全な有酸素運動というものは存在しない。(R)

ただし脚を太くしたいときにサイクリングやダンベルカールをする人はいません。なので特異性はあると考えてOKです
トレーニングで決めるべきパラメーター3つ

有酸素運動だろうと無酸素運動だろうと、トレーニングで決めるべき変数は3つです