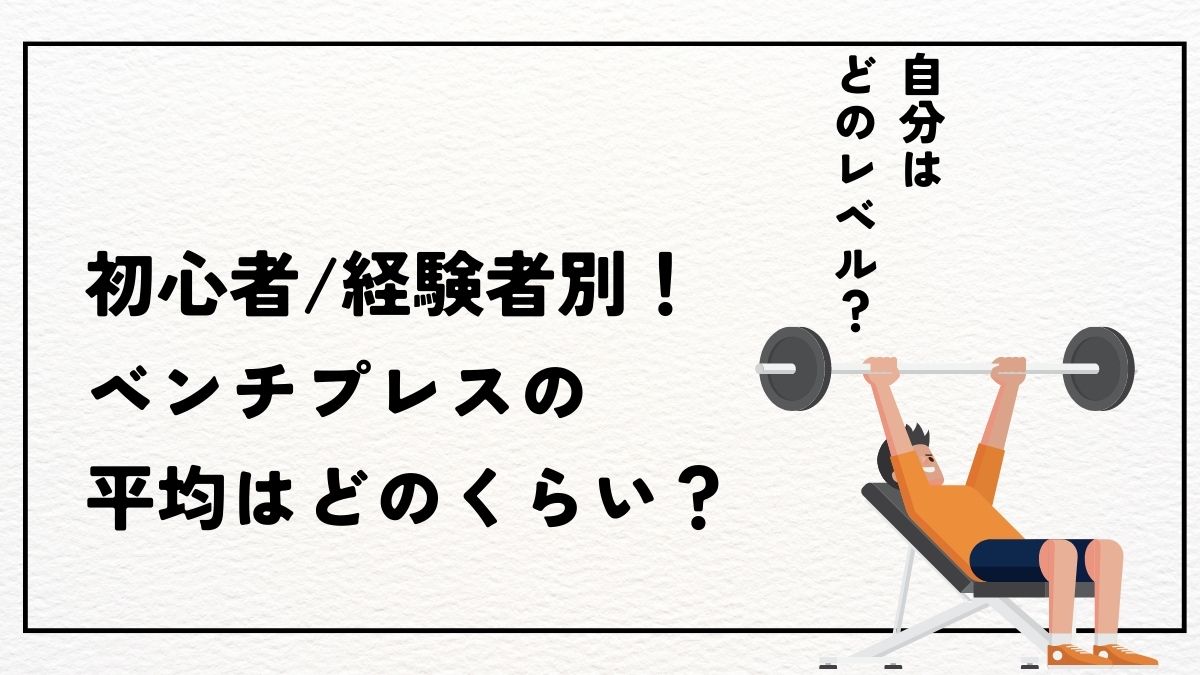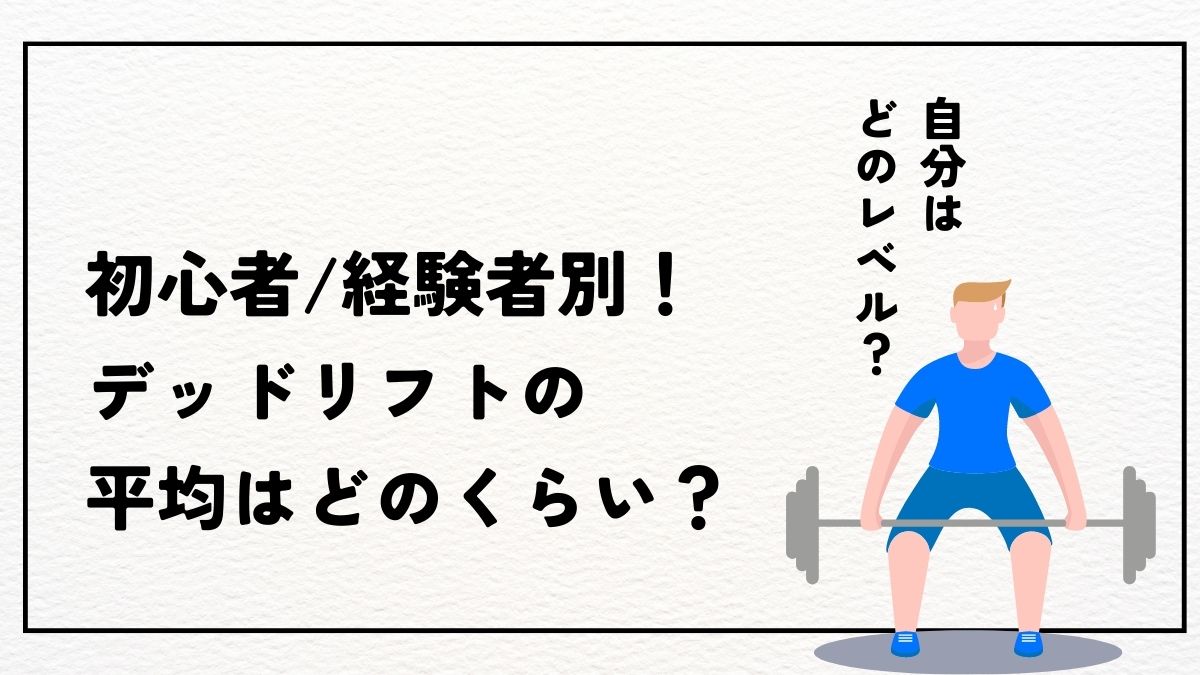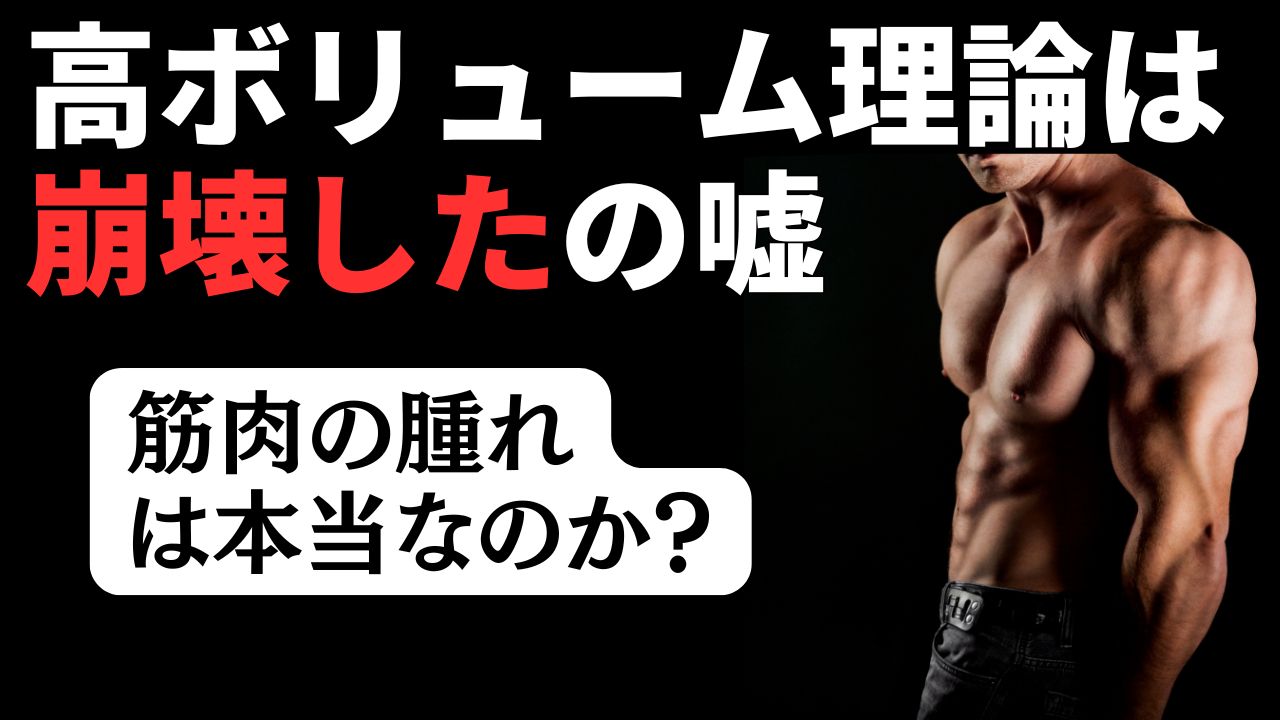筋肥大に効果的!当日の調子で筋トレを決めるオートレギュレーション
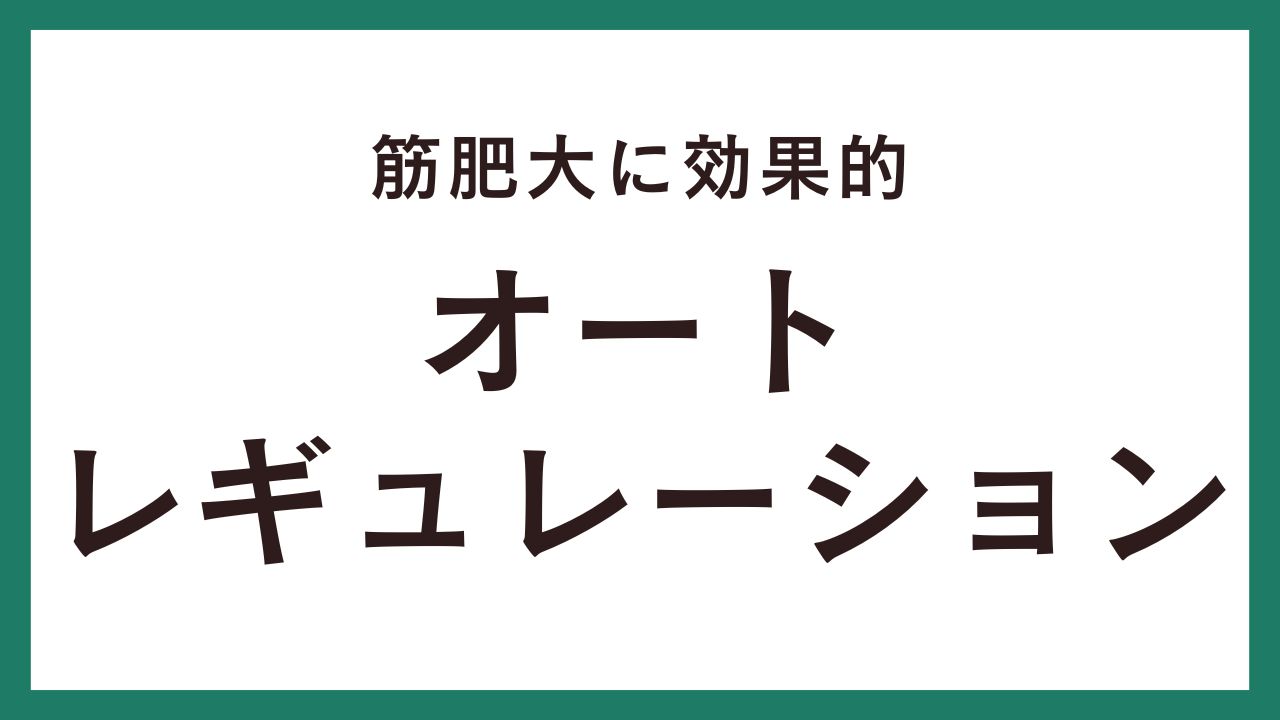
「今日は前回の筋トレよりも1%でも多くこなそう」
そう思って筋トレをしていないだろうか?
実は、このように筋トレするより、調子が悪い日にはむしろ少しトレーニング量を下げた方がいい。
仮に前回の筋トレより一時的に後退したとしても、である。
このように、その日の調子によってトレーニング量を変更することを”オートレギュレーション”という。
今回は、論文からオートレギュレーションに関する話を紹介しよう。
オートレギュレーションとは、日本語に訳すと”自動調節”。
トレーニングはむやみに頑張るより、オートレギュレーションでその日の調子に合わせる方が長期的には筋トレの成果が上がることがわかっている。
常に70kgでトレーニングは時代遅れ?
そもそもオートレギュレーションとは何なのかを知るために、まずは一般的なトレーニング方法から考えてみよう。
例えば、現在のあなたの能力がベンチプレスを70kgで10レップ行なえる程度だとしよう。
ベンチプレスで70kg10レップを続け、次第に楽にできるようになって11レップできるようになる。
そして、11レップを繰り返していくうちに12レップできるようになり、12レップをラクにできるようになった時点で負荷を2.5kgほど上げる。
そして72.5kgをまた10レップ行い、楽にできるようになってきたら11レップ行う。
この作業を続けていくことで徐々に負荷を上げていく筋トレをしている人も多いだろう。
実際にこの方法は筋トレで最も重要である”漸進性過負荷の原則”を満たしており、筋肉は十分につくだろう。
しかし、実はこの方法には欠点もある。
それは「常に70kgを10レップ行えるとは限らない」ということである。
というのも、私たちは人間なので当然体調がいい日もあれば体調が悪い日もある。
寝不足や仕事の疲れがたまっているときは、70kgを10レップというのはあまりに重いだろう。
逆に調子のいい日であれば、70kgを10レップでは負荷が足りないかもしれない。
それにもかかわらず、常に70kgを10レップというトレーニングメニューを組んでしまう人が多いのではないだろうか。
そこで、トレーニング量を一定にするのではなく、体調がいい日は多くのトレーニングをこなし、体調が悪い日はトレーニング量を少なくするようにトレーニングを組むのが”オートレギュレーション”である。
それでは、オートレギュレーションではどのようにトレーニング量を調整するのだろうか?
トレーニング調整法には
- 負荷を変動させる方法
- レップ数を変動させる方法
の2種類がある。
まずは、負荷を変動させる方法から見ていこう。
RPEによるオートレギュレーション①:RPEレンジ
負荷を変動させるということは、負荷を固定しないということである。
実は、99%の人はトレーニングの負荷を固定させている。
例えば、多くの人は強度の指標として毎回ベンチプレスを70%1RM(=70kg)などと決めて行っているだろう。
オートレギュレーションでは、このように負荷を固定しない。
負荷を固定する代わりに、RPEを固定するのである。(RPEについては以下を参照)
例えば、ベンチプレスの1RMが100kgの人で考えてみよう。
従来の方法ならば、70%1RM(=70kg)で10レップを3セット行う、といったようにトレーニングするのが一般的だろう。
しかし、RPEを用いたオートレギュレーションでは、6-8RPEで10レップ3セット、というようなトレーニングメニューの組み方をする。
このとき、負荷に関しては決まっていないのである。
調子がいい日は80kgで10レップがRPE8になるだろうし、睡眠不足や仕事の疲れを引きずっている日は60kgで10レップがRPE8になるかもしれない。
このように、その日の調子に合わせて決められたRPEに沿うように負荷を決める。
この方法はRPEレンジ(RPE Ranges)と呼ばれる方法で、強度の指標として”%1RM”の代わりに”RPE”を使うのである。
レンジとは日本語に訳すと”範囲”なのだが、事前に決めたRPEの範囲で負荷を決めることから、このような名前がついている。
あまり知られていないRPEレンジだが、実はこのように柔軟に強度を変更させることは固定負荷より優れているかもしれないことが最近の研究で明らかになってきている。
例えば2019年の研究では、RPEレンジを用いたグループは固定負荷グループに比べて、スクワットの筋力向上が大きかったことが報告されている(+9% vs +15%)。[1]
現在のフィットネス界隈では毎日同じ負荷で同じ回数行っている人が多いだろう。
しかし、実は強度はその日の調子によって柔軟に変更するほうが効果的な可能性が高いのである。
RPEによるオートレギュレーション②:RPEストップ
RPEを用いたオートレギュレーションには、レップ数を変動させる方法もある。