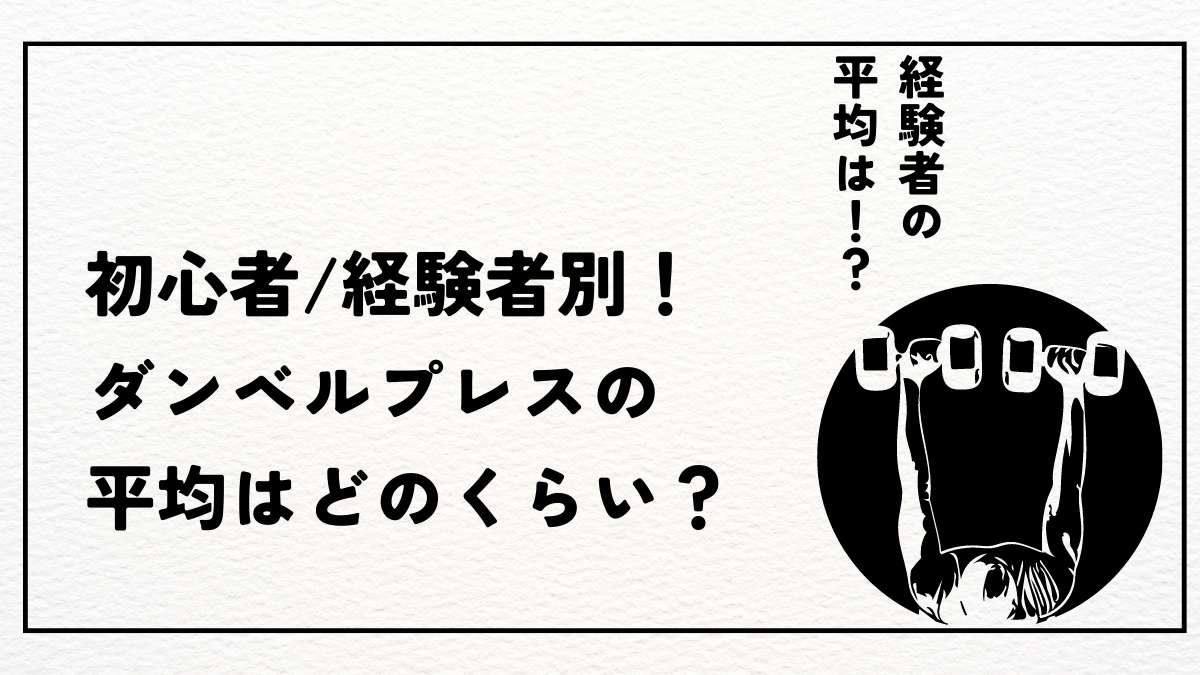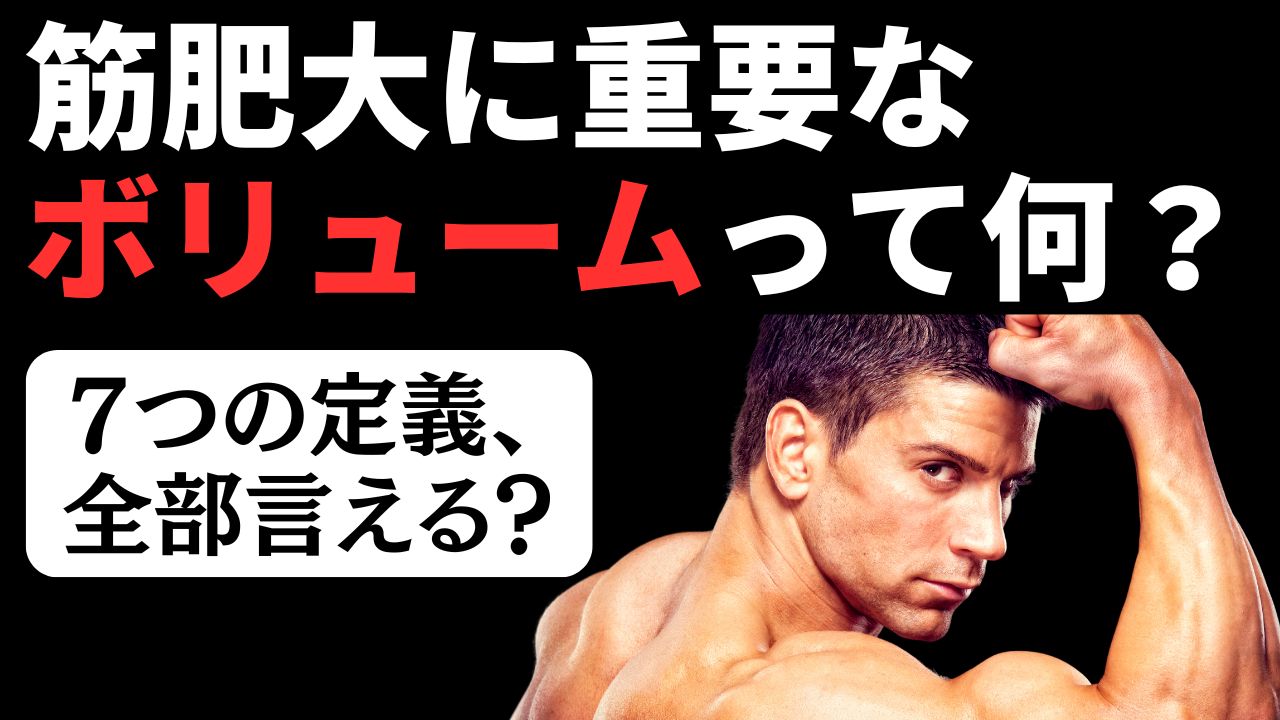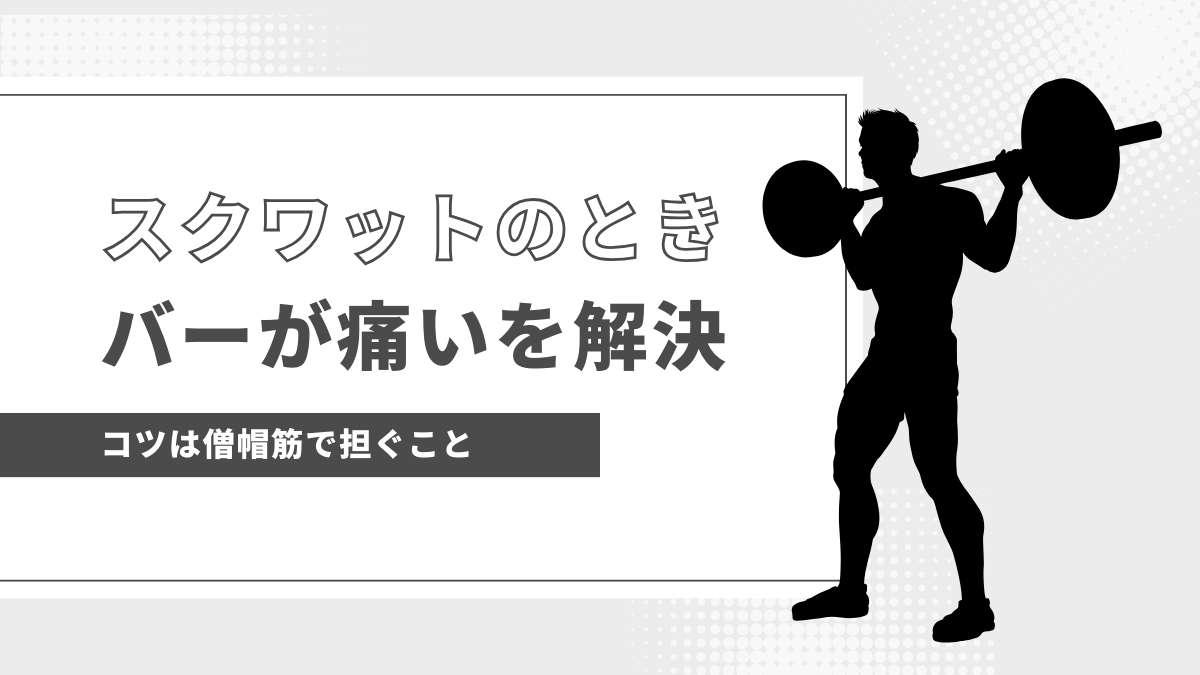筋トレのボリューム理論を徹底解説!理解のカギは定義を知ること
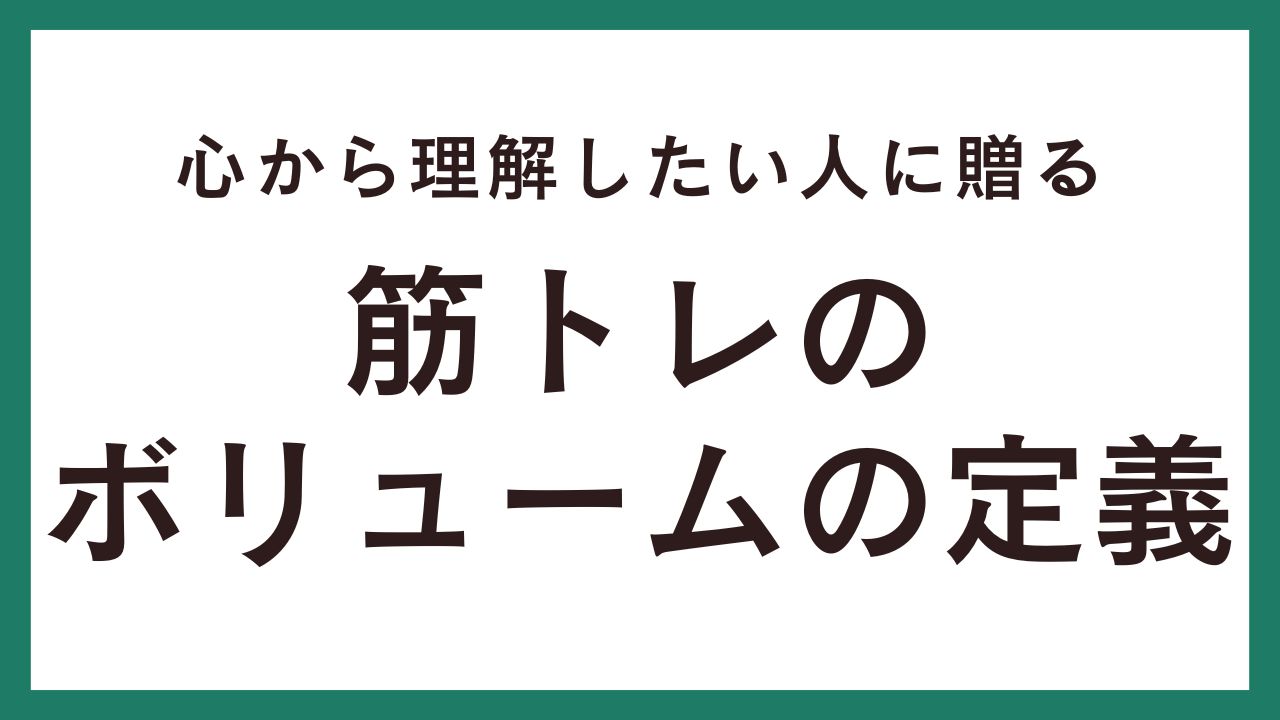
- ボリュームは研究者の机上の空論、筋肥大には関係ない!!
- ボリュームが筋肥大には一番大事なんだ!!
このように筋トレのボリュームに関しては議論が尽きないが、そもそも”ボリューム”って何なのだろうか?
「ボリュームとは〇〇のことです」の〇〇に入る言葉をちょっと考えてみてほしい。
- 〇〇に入るのは仕事量です!
- いやいや〇〇に入るのはセット数でしょ!
- 〇〇は重量×レップ数×セット数やろ
実はこれ、全部正解です
ボリュームという言葉の定義が曖昧なまま誰もが勝手なことを言っているので、情報が錯綜している。
ということで今回の記事では『そもそもボリュームとは何か?』を整理してみよう。
ボリュームという言葉を理解すれば、「筋トレは週に何セットするべきか?」も自分で判断できるようになる。
ボリュームってそもそも何?
ボリュームは筋トレを定量化しようとしたもの
ボリュームという概念を理解するために重要なこと。
それはボリュームが「筋トレの”量”を定量化したい!」という思いから始まっていることだ。
研究の世界では運動を”強度・量・頻度”で数値化したいというモチベーションがあります
運動の結果は有酸素運動だろうが無酸素運動だろうが「強度・量・頻度」で決まる。
というかこの3要素で運動をモデル化したいというのが正しいが。
| 運動 | 有酸素運動 | 筋トレ |
|---|---|---|
| 強度 | 心拍数 | %1RM |
| 量 | 時間 | ボリューム |
| 頻度 | 週何回か? | 週何回か? |
例えば有酸素運動は心拍数が強度の役目を果たしており、スプリントやHIITなどの心拍数が180くらいまで上がる運動は高強度だし、逆に心拍数が60くらいの歩行などは低強度。
筋トレでは心拍数では強度が正確に測定できないので、「MAXの重さの何%の重量なのか?」を強度の指標にしている。
そして量を測定する方法として、有酸素運動は基本的に連続して行うものだから時間を計測するという単純な方法が用いられている。
一方で筋トレは、休憩時間が時間の大半を占めるので時間を測定するだけでは”量”を測定できません。
例えば同じ30分間の筋トレでも、スクワットをセット間休憩5分で行った人と、スクワットをセット感休憩1分で30分間こなしていた人では筋トレの量が明らかに違うだろう。
それでは筋トレの量(=ボリューム)を表す指標として何が適切なのか?
実はこの問題はいまだに決着がついておらず、定量化しようと頑張った歴史の結果としてボリュームが乱立している状態なのだ。