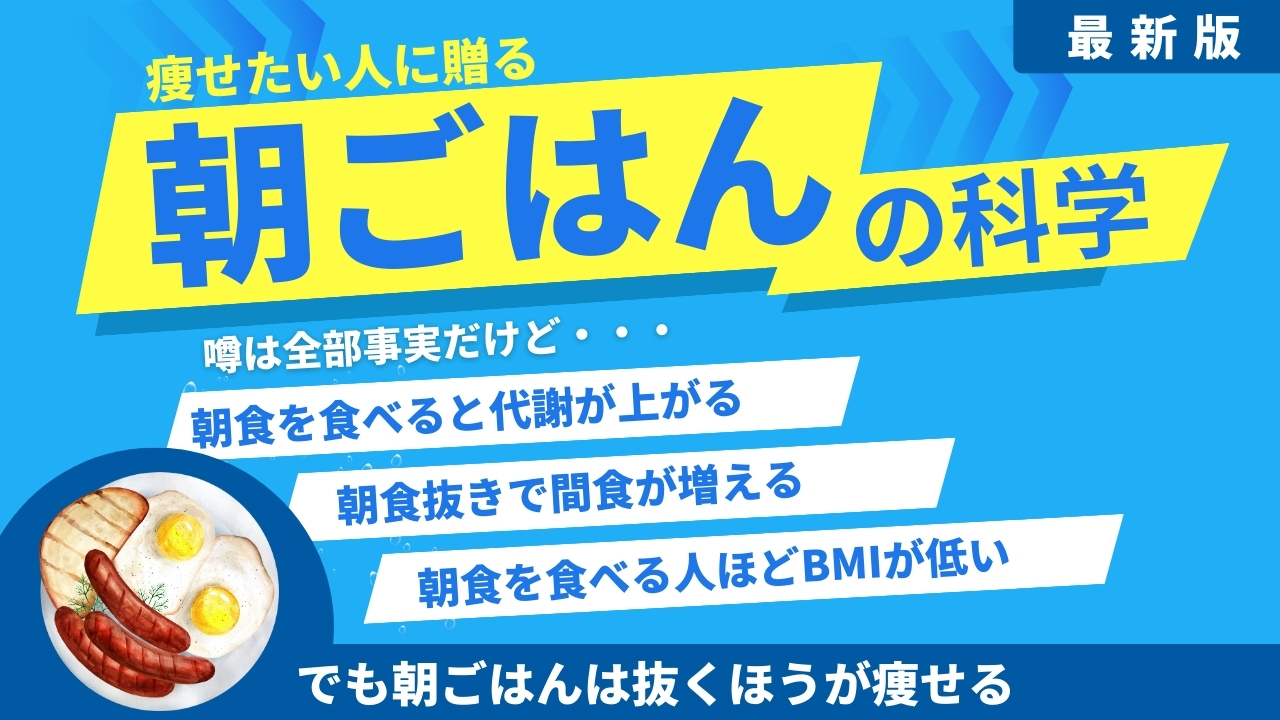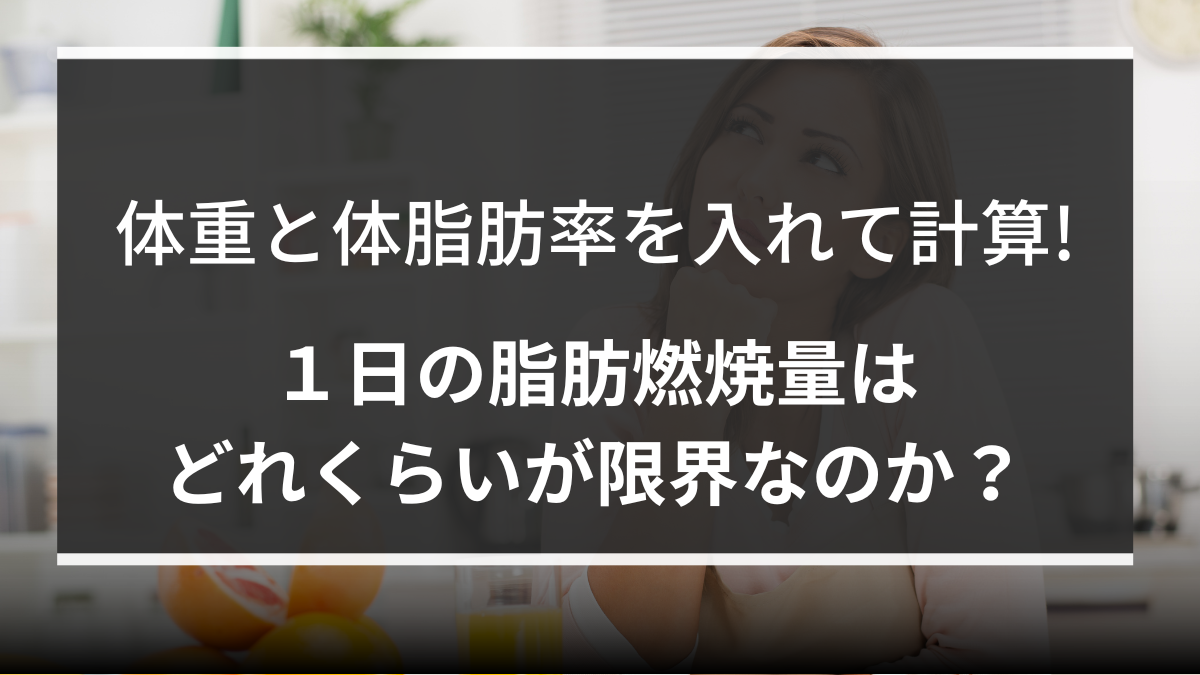食欲が止まらないときの対処法は?言い訳して食べちゃったをやめるには
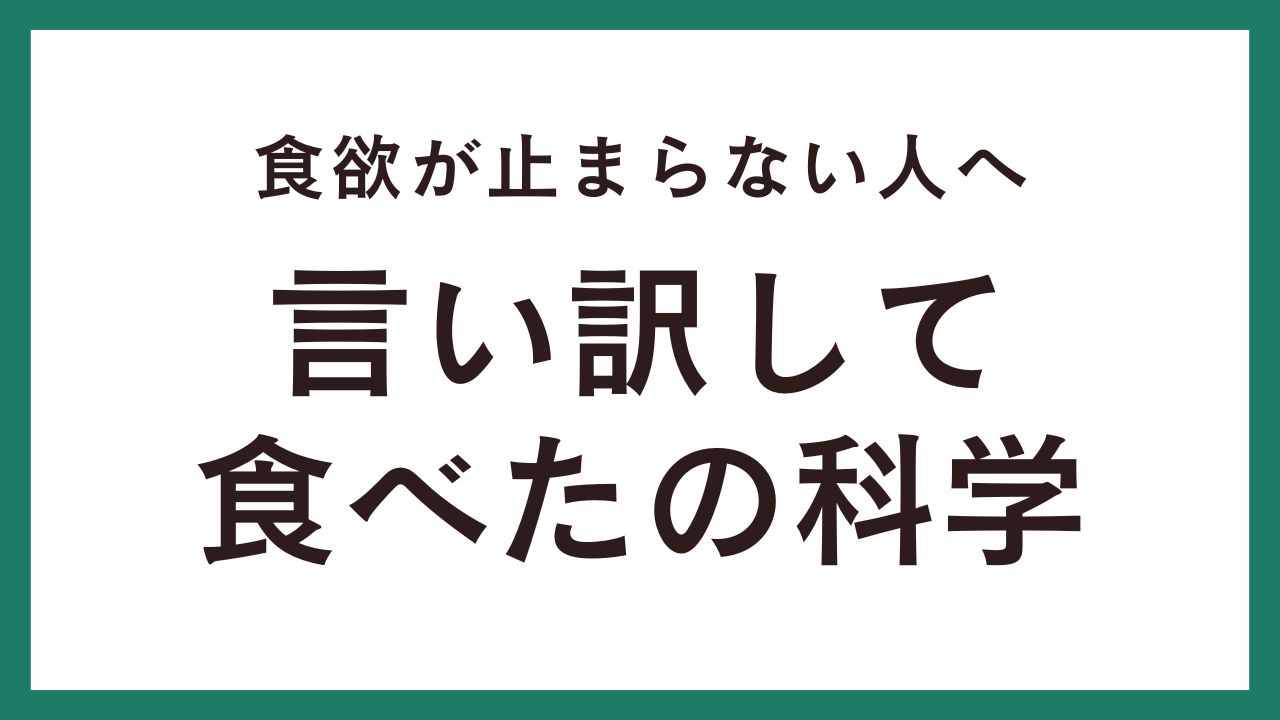
「ダイエットや栄養学の知識はあるのに痩せない」
「つい言い訳して食べ過ぎてしまう」
例えば、栄養や体のスペシャリストである医師や栄養士であっても、必ずしも健康的な痩せ体型であるわけではない。
いくら痩せるための方法論がわかっていても、実行できなければ意味がない。
しかし、つい食べ過ぎてしまうというのは私たちにとって日常茶飯事。
今回は、論文から「なぜつい言い訳して食べてしまうのか?」といった話題から、食欲に直面したときに負けない方法を紹介していく。
まずは、食欲に直面したときにやりがちな失敗例から見ていこう。
ダイエット中に食べたいとき、あなたはどうする?
ちょっとしたプチ減量でさえ、ダイエットをしていれば”食べたい”衝動に襲われることは多々ある。
それが本格的な減量ともなれば、それはそれは耐え難い食欲に襲われる。
実際現代には誘惑が溢れている。
スイーツ店の前を通り過ぎたときに目に入った美味しそうなケーキが載った立て看板を見るだけで、今日予定したカロリー量は全て食べたのに食欲が湧いてくるという困った事態になる。
- 今日は仕事を頑張ったしたまにはご褒美もいいかな
- たくさん食べるほうが代謝が戻るっていうし、たまにはスイーツもいいかな
こうした思考が浮かんでくるが、自分はダイエット中。
なので、食べない理由で食べる理由を却下しようとする。
- でも今日食べ過ぎたらダイエットが少し後退する
- お金を使い過ぎちゃうし、我慢しなきゃ
こうして、食べたい自分とダイエットしたい自分の”話し合い”が始まる。
もちろん、これでも食欲に勝てるときもあるかもしれないが、ほとんどの場合は食欲に負けて食べてしまうのがオチ。
なぜこの一見理性的な脳内の話し合いが失敗に終わるのか?
それは、脳にとって理由なんて後付けに過ぎず、その理由とは往々にして自分に都合の良い理由を採用するからである。
食べてから食べてしまった理由を考える
そもそも、食べたい理由に食べない理由をぶつけて食欲に勝とうとする方法は、理由が先にあって自分の行動が後にあれば成功するかもしれない。
多くの人がそんなの当たり前と思うかもしれないが、真実は違う。
実際は自分の行動に対して脳が後から理由づけをしているだけなのである。